こんにちは、隊長です!
今日は「いい子」についてのお話。
子どもが「いい子」に育ってほしいと願う
親はきっと少なくないでしょう。
でも「いい子」って本当に子どもの為に
なっているのでしょうか?
「いい子症候群」という言葉も最近聞くようになりました。
今回はこれからの子育てや子どもとの関わりにおいてとても重要なことを書きました。
少し厳しいことも書いています。
一意見として、参考になる部分があれば参考にしてください。
パパママ、学校・児童館・学童の先生など、子どもに関わる方は最後まで読んでみてください。
結論

私が言いたいことは、
「子どもを「いい子」に育てたい」は大人のエゴ!
子どもを主体に考え、子どもの気持ちに共感したかかわりをしましょう!
です。
子どもの育ちを主体にした考え、行動をとりたいものですね!
では解説していきます。
いい子は危ない?

わかりやすいように例を用います。
児童館でAちゃん親子とBちゃん親子の2組が楽しく遊んでいました。
帰る時間になったので親が子どもたちに「帰るよ」と声をかけます。
Aちゃんは「はーい」と、遊んでいたおもちゃを片づけ始めました。
Bちゃんは「嫌だ!」と、大泣きしてしまいました。
Bちゃんの親は「Aちゃんはなんていい子なんだろう」と感心して、「うちの子ももっと厳しくしないと」と思いました。
さて、AちゃんとBちゃんどちらがいい子でしょうか?
世間的にはきっとAちゃんがいい子と言われるでしょう。
では、Bちゃんは悪い子なのでしょうか?
違いますよね。
子どもの育ちの視点でいえば、Bちゃんは子どもとして当然の反応をしています。
自分の体の中に流れる負の感情エネルギーを「泣く」という行為で表現できているのです。
親としては大泣きされると大変ですが、
これはとても大切なこと。
このような場面では厳しいしつけよりも、「帰る」というルールは変えずに「悲しいね」「残念だね」と負の感情を言語化してあげる。
つまり子どもの負の感情を社会化してあげることが大事です。
むしろ心配なのはAちゃんです。
「まだ遊びたい」「嫌だ」「残念」「悲しい」といった負の感情はどこに行ってしまったのでしょうか?
無くなってしまったのでしょうか?
そんなことはありません。
なかったものにされた負の感情は、今後、何かのトラブルや出来事によって、暴力、いじめ、自傷行為など問題行動に形を変えて表出されることがあります。
運良く子どもの頃に問題行動が起きなくても、大人になってから養育不安などの形で表れることも。
Aちゃんは親や周りから求められることで、自分の感情より「いい子」を演じることを優先しているのかもしれません。
何か嫌なことがあったとしてもいい子なほど自分の考えや感情を外に出しません。
ですから学校の先生も、学童の先生も「手のかからないいい子」と判断しがちです。
気づいた時には問題が大きくなっています。
「いい子」ほど注意ましょうね。
なぜ「いい子」を求めるのか

多くの親や周りの大人は、いつも明るくニコニコ、ルールも守り、聞き分けもいい「いい子」に育つよう願います。
いい子に育てたいという背景には、
「いい子と褒められたい」
「親自身もそのようにしつけられて育てられてきた」
「周りからしつけがなってないと思われたくない」
「他の子はできるのになぜうちの子はできないの?」
「泣いたり、怒ったりしない手のかからない子になってほしい」
といった、
・親や周囲の人間の自己満足
・周りの評価を気にする
・他の子との比較
・親が子どもの負の感情を受け止められない
などの理由が挙げられます。
一度考えてほしいのは「いい子」になれば、子どもは本当に幸せなのですか?
どの理由も親や周囲の人間にとって都合のいいことばかりで、子どもが主体になっていません。
子どもはペットではありません。
子どもにとって何が幸せなことなのか、考えて行動することが大人に求められています。
社会が「いい子」を作り出す?

「理想のいい子」を求めすぎると、現実とのギャップに耐えられず子どものできないことばかりが目につくようになります。
「片付けなさい」「早くしなさい」とより厳しくあたってしまい、終いには子どもが可愛いと感じられなくなることもあります。
そうなると親も子も辛いことばかりです。
ただ、すべて親が悪いというわけではありません。
社会がそうさせている面もあります。
何をするにしても
早さ、効率、みんな同じ
を求められます。
Bちゃんのような子どもらしさに付き合ってあげられる時間や考え方、心の余裕が減ってきているように感じます。
他にも
「公園で遊んでる子どもがうるさいからなんとかしろ」
とか
電車で泣いている赤ちゃんの親が
「うるさい泣き止ませろ」
とか言われたり
どうしても周りの冷ややかな目を気にしてしまいがちな環境も増えています。
もうちょっと社会全体がゆっくり進み、子どもの成長を温かく見守ることができるゆとりがほしいですね。
最後に

今回は「いい子」についてお話してきました。
厳しいことも書かせていただきました。
でも皆さんは子ども一人ひとりの幸せを願っているはずです。
もちろん子育ては楽しいことばかりでなく、イライラ、しんどい、つらいがたくさんあります。
そんな時は深呼吸して、子ども主体のかかわりや共感することの大事さを思い出してくださいね。
少しずつで構いません。
「いい子」に育てるではなく、子どもらしさを認め、共感してあげてください。
きっとそれがお子さんの幸せにつながると思います。
以上です。少しでも参考になったら嬉しいです。
ではまた!
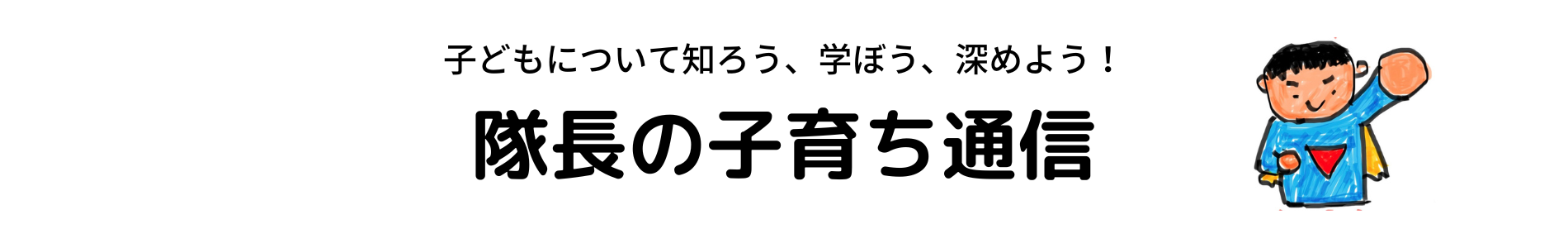


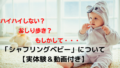
コメント