こんにちは隊長です!
今回は児童館・学童職員向けに
子どもの「やりたい!」を形にすることで
得られるメリットとその方法をお話ししたいと思います。
この記事を読むことで
・子どもの意見を尊重することの大切さがわかります。
・なぜ子どもの参画が必要なのか。
・どうやって形にしていくか学べます。
厚生労働省の児童館ガイドライン、第4章の3に「子どもが意見を述べる場の提供」が定めらています。
他にも各自治体の児童館運営指針やガイドライン等にも子どもの参画について記載がされるようになりました。
私たち職員は、子どもの意見を尊重し、子どもの参画に力を入れる必要があるのです。
では早速みていきましょう!
メリット
子どもの意見を尊重しながら、子どものやりたいことを形にしていくと得られるメリットは大きく分けると以下の3つです。
①子どもの自己肯定感が高まる
②周りの子への相乗効果が
得られる
③子どもとの信頼関係アップ
では順番に解説します。
①子どもの自己肯定感が高まる
やりたいことを子どもと一緒に形にしていく中で、準備や作業を伴うことが出てきます。
その量は「やりたいこと」のスケールに比例します。
例えば「卓球大会がしたい」と「おまつりがしたい」とではどちらが大変か容易に想像できるかと思います。
「卓球大会」は卓球台は児童館であれば大体あります。
あとはどう運営するかを考えればOKですが、「おまつり」となると何のブースを、いくつくらいで、何を用意すれば・・などたくさん考え、かなりの準備が必要になります。
やりたいことの準備や作業はとても大変なことです。
だからこそ葛藤しながら準備をし、「やりたいこと」が形になった時に子どもは達成感を覚え、自信がつきます。
この積み重ねで、「ちょっとくらい失敗しても大丈夫」「失敗してもなんとかなる」という自己肯定感が養われていきます。
NGなのは職員がおぜん立てしすぎることです。
あくまでも子どもの意見を尊重しながら支援していきましょう。
②周りの子への相乗効果が得られる
誰かのやりたいことを形にしていくと、
見ていた子が「いいなぁ」「うらやましい」「自分も○○したい」と周りへ広がっていきます。
他の子のやりたいも形にしていくことで、周りの子の自己肯定感も高まり、結果として職員主導の行事やプログラムだけでなく、子ども発案の行事やプログラムが増えていきます。
子どもの参画は、自主性・協調性・創造性等が養うとともに、子どもの心身の健やかな成長・発達及びその自立を図るために必要なことなのです。
子ども発の行事が多い児童館・学童は子どもたちが生き生きとしてます。
こんな施設が少しでも増えてほしいなと思います。
③子どもとの信頼関係アップ
子どもからしたら、自分のやりたいことのために一緒に頭を悩ませ、準備も手伝ってくれて・・苦楽を共にした人とは信頼関係がアップするのは当然なことです。
今後も困ったことや助けが必要な時、また何かやりたいことができた時は、頼りにされることでしょう。
職員冥利に尽きますね!
どうやって形にしていくの?
続いてどうやってやりたいことを形にしていくのかを解説します。
ポイントは以下の通りです。
①出会いと関り
②発見・提案
③調整
④準備
⑤実施
では順番に見ていきましょう。
①出会いと関わり

やりたいことを形にするのになぜ出会いと関わりが必要なんですか?

逆に聞くけど、あなたは全く知らない人・関係が薄い人にやりたいことを言えますか?

言えないですね・・

まずは子どもとの関係づくりから!たくさん関わって色々話せる間柄になりましょう!
②発見・提案

「○〇やりたい」って言ってくれる子はわかりやすいんだけど、
引っ込み思案な子にはどうしたらいいの?

関わりの中からその子の得意なこと、好きなことを見つけて、
今度「○○やらない?私も一緒に手伝うよ」と声をかけてみましょう!

私の体験談の紹介。
昔、ピアノが上手な子がいたんだけど、なかなかの引っ込み思案。
「児童館のお楽しみ会で弾いてみない?」
「私が曲に合わせてカスタネットたたくから、一緒にでない?」
と何度も誘ったところ、
「じゃあ、出てみようかな」と
OKくれました。
当日はピアノの上手さに、みんなから拍手もらって「出て良かった」と喜んでましたよ!

そんなこともあるんですね!
関わりの中から、その子の得意・好きなことを見つけてみます!
③調整

子どものやりたいことが突拍子もなくてどうしたらいいんですか?

そうそう、ここが一番大変なんだよね(笑)
でも大事なことは「まずはすべて聞き、否定しないこと」です。
すぐに「できない」って言われたら、もう次から言ってくれなくなることがあります。
「どうやったらできるかな?」と真剣に考える。この思考の癖をつけましょう。
その上で、自分、自分の施設で提供できる最大限の資源や援助、それを行うにはどんな準備・作業、どれくらいの日程が必要になるのか具体的に提示しましょう。
そうすることで子どもが現実を知って妥協案や違うやりたいことを提示しやすくなります。
子どもも言ってしまった手前、意見をひっこめられなかったりしますから。

子どもと意見のすり合わせをしながら、落としどころを見つけるんですね!

そうです。
あと、できればレスポンスは早いほうがいいです。
「鉄は熱いうちに打て」です。
保留にする期間が長ければ長いほど子どもの熱は冷めていきます。
自分の裁量では決められない時は施設長にすぐ相談して次の日くらいにはどうなったか子どもと話しましょう。
中には、申し訳ないけどできないこともあります。それは素直に伝えましょう。
④準備

子どもと一緒に準備する上で気を付けることはありますか?

簡単なものは時間をかけず、子どもと一緒にどんどん準備していくこと。
「鉄は熱いうちに打て」です。
難しいもの・時間がかかるものは、準備・作業スケジュールを立てること。
日数かかるものはどうしてもモチベーションの維持が大変ですから。
子どもが飽きないように且つ適切な日程や作業量を決めるのが大事ですね。
高学年には企画書作らせたり、準備・作業も何が必要か考えて取り組んでもらったりしますね~。
また、準備においては子どものやりたいことを尊重しながらも、計画から外れすぎないように手綱を握る必要はあります。

・鉄は熱いうちに打て
・準備の見える化
ですね!
⑤実施

もう準備もバッチリだから何もしなくていいですよね?

意外とそうでもないんです。
不測の事態が起こることは十分ありえます。

そうなの!?

これも体験談ですが、子どもと一緒に十分に準備しても「当日、本人が来なかった」こともありますよ(笑)
今までの苦労は・・って感じですが、そこは子どものやることですからしょうがないです。
なので職員は当日は見守りつつ、うまくいくように支援するほか、別案等も考えて準備しておきましょう。
最後に
今回は子どもの「やりたい!」を形にすることのメリットとその方法を解説しました。
1つ付け足しで、もし子ども会議の場(大勢の場)等でやりたいことを募る場合、子どもたちに「人の意見を笑わない・バカにしない・否定しない」「意見を言いたいときはどうしたらもっと良くなるかを言う」をルール化しておくと、子どもも安心していろんな意見を言ううことができます。
これすごく大事です。
最後に、「やりたい」と言える子は、実はもともと自己肯定感が高めな子です。
もちろん高めな子の「やりたい!」も形にするよう支援しますが、私たち職員が本当に支援する必要があるのは自己肯定感が低めの子です。
この子たちは自分から「○○したい」ということは少ないです。
だからこそ、日々の関わりを密にしながら得意なことや好きなことを見つけ、自信がつくように・自己肯定感が高まるような場を設ける必要があるのです。
日々の関わりを大事にしながら、「やりたい!」を形にしましょう!
ではまた!
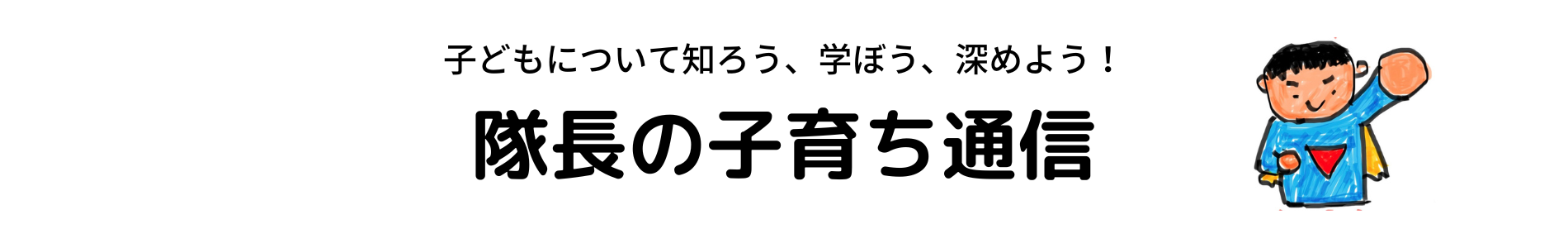



コメント